形は出来上がりましたか?
これから完成へ向けて、すこぶる地味だけど大事な作業『ヤスリがけ』をします。
本気で地味です。
正直飽きます。
でもココでの頑張りが明日の仕上がりの差として出てくるのです。
がんばりましょう。
やすりは数字の小さい順から大きい順に目が細かくなっています。
見れば分かりますか、そうですね。
ピンキー改造だと400〜1000番の間で3枚ほど用意しとくと良いそうです。
目が大きめのヤスリで大まかにヤスッて下さい。
↓のように短冊状にして目の荒さを書いておくと使う時いちいち切らずにすんで便利です。

ヤスリ作業ではスピンヤスリが大活躍です。
コレを使うと作業が楽しー!!
芸人サンダーも使い勝手が良かったので合わせて作ってみると良いかも。
この作業では激しく粉が舞います。
肺に入ると体に良くないらしいのでマスクなどを装備した方が良いらしいです。
私は作業中に暑苦しくなって最終的にはしませんでしたが。
水とぎにすればかなり粉塵は抑えられます。
軽くヤスリをかけた所で『溶きパテ』の登場です。
ラッカーパテ、プラパテ、サーフェーイサーなど呼び方が色々あります。
私の場合はエポパテ部分との色の差があった方が
凹んでた部分が分かりやすいとの理由でMr.サーフェイサー500のグレータイプを使用しました。

コレを筆でペソペソと塗っていきます。
気になる傷部分には多めに塗っておきましょう。
傷を埋めてくれます。
ただし、このラッカー系のパテは『ヒケ(収縮)』が大きいので注意して下さい。
そしてラッカー系だけあって、とても臭いです。
窓を開けて換気を良くしておかないと気分が悪くなります。
そして火気も厳禁です。
タバコ吸いながらとかダメですょ。
ハァ?タバコ吸ってた方が集中できんだよ!!とか言う人も我慢して下さい。
集中力がそんなに必要な作業じゃないんで。
溶きパテの伸びが悪い場合はMr.カラー薄め液を筆に含ませて伸ばします。
ムラがあってもキニシナイ!!
そしてこの薄め液もまた溶きパテに負けず劣らず臭いので注意が必要です。
コッチも火気厳禁ですよ。
内キャップの2箇所に小さく穴を開けて使うと1滴づつ出せて便利なのでオススメです。
卵パックが塗料皿にも筆洗い用の容器にもなってとてもイイ感じです。
溶きパテが付いた筆の洗浄も薄め液で行って下さい。
水じゃダメですよ。
筆洗いに使った薄め液も排水溝には流さず、ティッシュなどに含ませて燃えるゴミへ。
溶きパテが乾きましたらまたヤスリ作業の再開です。
目の大きいヤスリから順に使っていきましょう。
全体をヤスってつるつるしてきたらもっと目が細かいヤスリで〜の繰り返しです。
音で表現すると『つるつる』→『とぅるとぅる』→『とぅるんとぅるん』みたいな。
先程の溶きパテで凹みや傷が埋まった部分はグレーのまま残り
エポパテの部分との継ぎ目に段などは無くつるつるになっていきます。
見た目は↓のように

斑ですが触ってみるとつるつるになので、ココで匂いに耐えた甲斐を感じてください。
あーこんなに凹んでた部分があったのか・・っと感慨にふけるもよし。
でも、もし溶きパテ使うのが面倒でしたらしなくても良いと思います。
その分ヤスリを念入りにすればなんとかなると思います。
まぁやっといて損は無いかなーっと。
ヤスリ作業自体ドコで妥協するかだと思うので、ご自身の判断でヨロシク。
っと言う訳で、ヤスリ続けて飽きた!!
もしくは、もぅ完璧★
あるいは、もうココで終わりで良いやー。
っと思った辺りで次の作業に入ります。
ここら辺は個人の判断です。
ひたすらヤスリかけるだけなので面白くないですしね。
気持ち、分かります。
パーツを磨き終えて粉などを洗って落とした後に
いよいよサーフェイサーをかけましょう。
私が使用したのはコレ↓
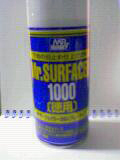
Mr.サーフェイサー1000の缶スプレータイプです。
先程使った溶きパテは500でしたが、1000はもっと粘度の低い物です。
数字が大きくなるに連れて粒子が細かくなっているんだそうです。(確か・・・
いきなりホワイトサーフェイーサー吹いても良いんですが
グレーを吹いた方が傷が見つけやすくなるそうなのでまずはグレーを。
吹く時の注意ですが、まず外で吹く事。
設備の無い家の中で吹くと大変なことになるそうです。
溶きパテの時点でかなりキツイ匂いなんですからソレを部屋中に撒くと考えたら当たり前かなぁと思います。
家の中で吹けば家族の迷惑になること請け合い!!
そして、風が無く天気の良い日にやった方が良いそうです。
模型サイトに書いてあるのですから、先人の教えって事で何か理由があっての事なのでしょう。
また、ダンボールを使えば埃をカット出来るそうですよ。
毎度お馴染みラッカー系なので手や衣服に付いても良いように対策をしましょう。
具体的には髪を染める時に付いてくる様な手袋をするとか。
手袋が無かったらビニール袋でも良いかと。
パーツは割り箸などで固定して手で持てるようにすると良いと思います。
前髪パーツだったら後頭部とのジョイント部。
後ろ髪は頭部との接続部。
上半身パーツなら首穴部分に直で棒を挿したり。
下半身は上半身とのジョイント部等、意外と挟めたり挿せたりするトコがありますんで。
吹き終わったパーツを置ける場所も用意しておきましょう。
さて、準備はできましたか?
ではサフを吹きましょう。
ダンボールで埃を防ぎつつ、パーツを右手に。左手にサフを。
パーツとサフは20〜30cmほど離して下さい。
↓分かり難い図ですが無いよりはマジだと思って下さい。
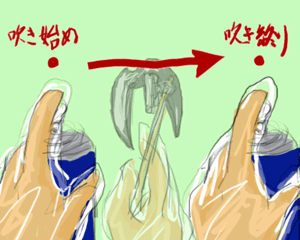
こんなカンジで吹きはじめと吹き終わりがパーツには掛からないように
スプレーを平行移動させて吹き付けます。
缶のガス圧が吹き始めの一押しと噴き終わりの指を外した瞬間が不安定だからだそうです。
一定方向に吹くだけにしといたほうが良いかと。
往復させたらボテッとした仕上がりになってしまったので・・・。(涙
遠すぎると表面がボコボコになってしまい、近すぎると多く付きすぎて垂れます。
吹き方ですが、シューーーーーーーーッッと長々と吹くよりは
シュッシュッと短く吹いて下さい。
そして吹くたびに良く振って下さい。
カラカラシュッシュ★ッとリズミカルに。
そして、くるくるとパーツを回して満遍なく吹き付けます。
薄く、数回に分けて吹いた方が綺麗に仕上がります。
失敗すると↓みたいになります。

またヤスリからか・・・っと激凹。
吹き終わってから乾かし、傷等のチェックをします。
全体がグレーになったので傷等も見つけ易くなっていると思います。
発見したら溶きパテやヤスリを再度使い、傷を無くして下さい。
そしてその後、再度サフを吹いて傷が修復されていれば下地完成です。
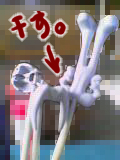
サフ前↓

サフ後↓


ぶっちゃけこの後にホワイトサフを吹こうと思ってたんですが
某大カメラ屋で品切れだったので今回は吹きません。
多分吹いた方が塗料の発色が綺麗になると思います。
ついに次回は最後の作業
→5.塗装へ。